
ここだけの話、今回はこんな話です
2025年3月以降、精神障害による障害年金の不該当者が増加しているという報道が頻繁に行われています。
本当にそうなのでしょうか?
前回のコラムでは、これらの報道について、私たちの現場での実感とは少し異なるとお伝えしました。
-

-
障害年金の審査が厳格化?報道では指摘されない「みんなのねんきん」の現場の実感とは
ここだけの話、今回はこんな話です 2025年3月以降、精神障害による障害年金の不該当者が増加しているという報道が頻繁に行われています。 中には、2024(令和6)年度の障害年金の不支給決定が3万件にな ...
続きを見る
報道を受けて、その後、この問題は国会でも取り上げられ、厚生労働省による実態調査が行われました。
そして2025年6月11日、その調査報告書が公表されました。
今回のコラムでは、この調査結果を障害年金の専門家としてどう読み解くべきか、そして、これから障害年金を請求しようと考えている方が本当に知っておくべきことは何かを、詳しく解説していきます。
ここだけの話、厚労省の調査結果のポイントとは
調査結果の重要ポイントは3つ
まず、公表された「令和6年度の障害年金の認定状況についての調査報告書」(以下、「報告書」)の重要なポイントを3つに絞って見ていきましょう。
調査は、全数ではなく、令和6(2024)年度の事案から、傷病を限定せず無作為に1,000件抽出し、分析したものになります。
精神障害の「不該当率」は実際に上昇していた
報告書によると、令和6年度の新規請求における不該当(不支給)の割合は13.0%と、令和5年度の8.4%から大きく上昇していました。
特に精神障害においては、不該当率が令和5年度の6.4%から12.1%へと、ほぼ倍増していることが明らかになりました。
これは、前回のコラムで述べた「私たちの実感とは異なる」という点とは違う、厳しいデータが公式に示されたことになります。
組織的な「審査厳格化」の指示は確認されなかった
一連の報道では、日本年金機構のセンター長交代による「審査の厳格化」が不支給増加の原因とされていました。
しかし、報告書では「審査を厳しくすべきといった指示を行っていた等の事実は、確認できなかった」と結論付けています。
ただし、センター長から「認定の根拠を明確にすべき」といった趣旨の指摘はあったとされています。
不支給増加の中身
では、なぜ不支給は増えたのか。
報告書で最も注目すべきは、精神障害の不支給事案の中身です。
「障害等級の目安」よりも下の等級と判断されて不支給になったケースの割合が、令和5年度の44.7%から令和6年度には75.3%へと急増しています。
目安というのは、診断書や日常生活の状況から「この場合なら2級が目安」という具合に、判定のための基準のこと。
ただ、絶対的な基準ではないため、下の等級に判断されたとしても問題はありません。
総合的に判断した結果、目安から外れるということもあり得ます。
「指示はなかった」が「仕組み」に問題があったことが真相か
報告書では「上層部から審査を厳しくしろ、という指示は確認できなかった」と結論付けられています。
これだけ聞くと「じゃあ問題なかったんだ」と思ってしまうかもしれません。
しかし、話はそう単純ではありません。
今回の調査報告書の最も重要なポイントは、「指示」は否定しつつも、その指示を実現する「仕組み(プロセス)」に欠陥があったことを事実上認めた点にあります。
報告書は、今後の改善策として以下の点を挙げています。
- 職員が事前に作る「等級の案」の記載をやめる(精神障害)
- 「認定医に関する文書(医師の傾向をまとめたメモ)」を廃止する
- 不支給の判断は、必ず複数の医師で行う
- 担当する医師の割り振りを無作為(ランダム)にする
もしこれまでの仕組みに問題がなかったのなら、これほど大きな変更が不要なはず。
これらの改善策は、裏を返せば、これまでの仕組みが「判断の誘導」や「不公平な審査」を生み出す危険性をはらんでいたことを、国が自ら認めたことに他なりません。
特に、職員が作成する「等級案」は、その後の医師の判断に極めて強い影響を与えていた可能性が指摘されています。
これは、申請の内容から医師でもない職員が「この内容からはこの等級が妥当」「この症状では不該当が妥当」という案を事前に作成し、その後の医師の判定に先入観を与える文書のことです。
実際、不支給とされた精神障害のケースでは、最終的な医師の判断が、職員の作った「等級案」と一致していた割合が約9割にのぼっていました。
なぜ精神障害の不該当率が上昇したのか?
この問題の根本は、障害年金を審査する側の「仕組み」だけに原因があるのではありません。
「申請する側」の変化も大きく影響しており、この二つが相互に作用してしまった「良くない状況」が生まれたと考えます。
考えられる背景事情を見てみましょう。
障害年金の認知度向上による申請者の急増
かつては周囲と話をしていても「障害年金ってなに?」というのが普通でした。
ところが、近年、SNSなどで障害年金制度の認知度が上がったと思えます。
認知度が上がれば、「自分でも申請してみよう」と申請のハードルが下がります。
特に精神・知的障害の新規申請は、令和4年度から5年度のわずか1年で約1.2万件も増加しています。
申請内容の質の変化
申請が急増する中で、残念ながら書類の準備が不十分なケースや、客観的な医療記録と本人の申告が食い違うケースも増えてしまいました。
障害年金の審査の現場からは
「症状の軽い人の請求が増えている」
「カルテを見ると(申告内容と)違うことが書かれている」
といった声が上がっていたとのことです。
病気や障害が残ったからといって、即障害年金というわけではありません。
制度が規定する障害状態に該当しなければ障害年金の受給はできないのです。
われわれ専門家が手続代行をする場合は、明らかに受給が不可能なケースでは本人にその旨を説明し、申請を見送ることもあります。
ノウハウが無い方がなんでもかんでも申請してしまえば、申請内容が不十分であったり矛盾があったりすることは容易に想像できます。
懐疑的となった審査
こうした状況を受け、審査する側は
「この申請内容は本当に正確だろうか?」
と、より慎重に、言い換えれば“疑いの目”で書類全体を見る傾向が強まったようです。
とすれば必然的に審査が厳しくなり、不支給事案が多くなることが予想できます。
審査の厳格化が連鎖
この懐疑的な姿勢が、前述の「事前確認票」という仕組みを通じて、具体的な審査行動に反映されたと思われます。
その結果、本来であれば支給されるべき境界線上の正当な申請までもが、この厳格化の波に巻き込まれ、不支給と判断されるケースが増加してしまったと言えます。
報告書からは、「障害等級の目安」よりも下の等級と判断されて不支給になったケースが増加とあります。
“疑いの目”で見るため、診断書に書かれた、等級の「目安」だけではなく、診断書や申立書、時にはカルテの内容まで踏み込んで、より総合的・実質的に障害状態を判断していることを示唆しています。
これらが、今回の不支給増加問題の根深い本質と私は見ています。
ここだけの話、みんなのねんきんはこれからの障害年金申請をこう考える
この大きな変化の潮流は、私たち障害年金の専門家に一つの現実を突きつけます。
それはまさに、「(障害年金に該当するであろう)診断書さえあれば大丈夫」という時代の終わりであり、「(不支給とならない)スキのない申請書類」が不可欠になったということです。
これまでは、医師の診断書が障害年金決定のウェイトを占めていました。
したがって、診断書の内容が障害年金の基準に達していさえすれば、申請には問題ないだろうというのが一般的な社労士の判断だったのです。
これからは、診断書はもちろん、その他の申立書を含めた申請書類一式において、障害年金を受給できるような内容になっていることが不可欠です。
では、具体的に何をすべきでしょうか。
私の考える、これからの障害年金申請における「新常識」を3つのポイントで解説します。
新常識1 「病歴・就労状況等申立書」が主役に
これからの精神障害の審査では、審査の方向性を左右していたかもしれない「職員による等級案」が廃止されます。
これは、認定医があなたの状態を判断する上で、「病歴・就労状況等申立書」の重要性が飛躍的に高まることを意味します。
この申立書は発病から現在に至るまで、時系列で病状をまとめた自己申告書です(医者に書いてもらうものではありません)。
これからは、この申立書がよりダイレクトに認定医の目に触れることになるでしょう。
単なる病歴の羅列ではなく、診断書の内容を補強し、日常生活や就労でいかに困っているかを具体的に伝える”プレゼンテーション資料”として、これまで以上に緻密に作成することが求められます。
新常識2 申請内容の矛盾は命取りに
今後の不支給決定は、必ず複数の認定医が関わることになります。
これは公平性を高めるための措置ですが、逆の見方をすれば、申請書類全体の内部的な整合性が、絶対的に重要になるということです。
一人の審査官なら見逃したかもしれない、診断書と申立書の間のわずかな矛盾も、二人の目でクロスチェックされれば、簡単に見抜かれてしまいます。
質の低い内容や矛盾を抱えた内容では、障害年金の受給は今より一層困難となるでしょう。
新常識3 「働いている」という事実だけで判断されない
障害年金は、一般的には、就労していると受給は難しいと言われています。
ただ、障害年金の審査において、就労していることをもって不支給になるという基準にはなっていません。
実際、「働いているから不支給になる」と心配される方は多いですが、問題はそこではありません。
例えば、診断書の目安では明らかに2級相当と判断できる方が、月に6万円程度の軽作業をしていることを理由に不支給とされた事例です。
これは、「どのような具体的な配慮や援助があって、初めてその月6万円の軽作業が成り立っているのか」という”月6万円の軽作業”の背景事情を、審査側が理解できなかったことが原因です。
逆に言えば、「月6万円の軽作業ができているが、様々な配慮や援助があるから重い障害状態でも例外的に就労できている」と審査側が納得できるような内容となっていれば、就労していても障害年金に結びつくわけです。
これはひとえにどのような申請書類を作成するか、作成者の力量にかかってきます。
ここだけの話、今回のまとめです

今回は、障害年金を請求する際の診断書の重要性について解説しました。
ポイントは以下のとおり。
- 報告書によれば、精神障害の不支給認定は増えているが、上層部からの指示があったことは認められなかった
- 職員が障害年金決定案を事前に作成する仕組みに問題があったと思われる
- 「(障害年金に該当するであろう)診断書さえあれば大丈夫」という時代が終わり「(不認定とならない)スキのない申請書類」が障害年金を左右する
厚生労働省の報告書は、障害年金審査が大きな転換点を迎えたことを明確に示しました。
「公平化」に向けた動きは、逆説的に、申請書類の質の差が、これまで以上に結果を峻別する時代の到来を意味します。
論理的で証拠に裏付けられた質の高い書類は、複数の審査官から正当な評価を得やすくなるでしょう。
一方で、杜撰な書類は、より厳しい判断を受けることになります。
この潮流の変化を正しく理解し、ご自身の状態を客観的な証拠に基づき、矛盾なく、かつ丁寧に伝えること。
それこそが、今の状況でご自身の権利を守るための唯一の、そして最善の道です。
手前味噌になりますが、みんなのねんきんで不支給となる事例が少ないのは、まさにこの点を日々追究しているからです。
私たちは、まずお客様のお話を徹底的にしっかりと聴き取り、ご本人も気づいていないような日常生活の困難な状況を引き出します。
その上で、診断書や他の資料と一切矛盾のない、まさに「スキのない申請書類」を作成することに全力を注いでいます。
参考にした資料
-
-
「令和6年度の障害年金の認定状況についての調査報告書」を公表します|厚生労働省
www.mhlw.go.jp

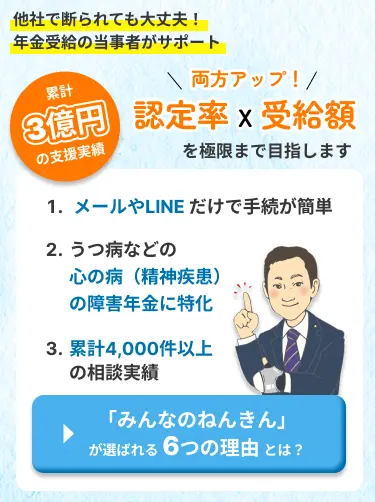
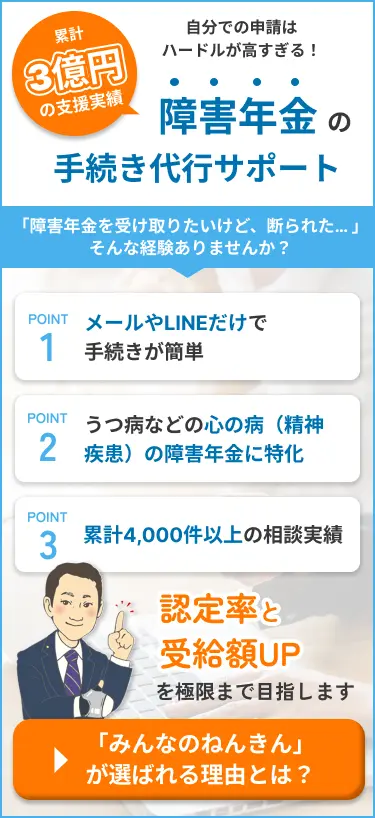

岡田真樹
みんなのねんきん社労士法人代表