
ここだけの話、今回はこんな話です
障害年金は一度決定されても生涯にわたって受給できるわけではありません。
障害の状態によって、数年ごとに更新の手続きが必要だからです。
この更新手続きには不安が伴います。
なぜなら更新によって、減額されたり、年金を停められてしまうこともあるからです。
今回のコラムでは、2回にわたり、更新手続きに伴う深刻な不安の核心に迫ります。
更新手続きの提出が遅れてしまったらどうなるのか?
そして、特に精神障害を抱える方々にとって、更新手続きがどれほど困難なのか。
その「問題」の正体を、専門家の視点から深く、そして具体的に解説していく「前編」です。
ここだけの話、障害年金は定期的に更新があります
障害者にとって更新手続きはストレスの種
障害年金を受給されている方のご自宅に、ある日、日本年金機構から一通の封筒が届きます。
中に入っているのは「障害状態確認届」。
一般に「更新」と呼ばれる手続きの案内です。
多くの受給者にとって、この書類の到着は、生活を支える大切な障害年金が再び審査の対象となる、大きな不安の始まりを意味します。
障害年金を受け取るための最初の申請手続きは、ご自身の障害を国に認めてもらうための一度目の「闘い」でした。
しかし、更新はそれとは質の異なるストレスを伴います。
それは、一度手にした生活の糧を失うかもしれないという、守りの「闘い」だからです。
更新手続きは、それ自体が大きなハードルとなり得ます。
特に、障害を抱えながら日常生活を送る方々にとって、厳格な期限が設けられた更新手続きは、精神的な健康をさらに悪化させかねないほどの重圧となります。
この不安の正体は、単に「年金が止まるかもしれない」という恐怖だけではありません。
複雑な制度への戸惑い。
重要な書類で致命的なミスを犯すことへの恐れ。
そして万が一、等級が引き下げられた(減額)、支給が止められた場合の生活への計り知れない影響、これら全てが絡み合った「手続きそのものへの不安」なのです。
更新が必要ない障害年金もある
ただ、すべての障害年金受給者に更新が必要となるのか?といったらそうではありません。
例えば、私は左手の親指以外を欠損した障害がありますが、この場合は「永久固定」ということで更新が必要無いのです。
では、更新が必要な障害とはどのようなものでしょうか。
簡単に言えば、障害年金決定後も症状の変化があるものが更新の対象になるのです。
障害年金の受給者の6割は精神疾患を原因としたものですが、精神障害は症状に波があります。
したがって、精神障害の場合は更新が必要なのです。
私のこれまでの経験では、精神障害の障害年金は2年から3年くらいの間隔で更新の機会が訪れます。
ちなみに、更新時期は初回の年金決定時に年金証書に記載されています。
更新手続きの期限を守れなかったらどうなる?
更新手続きの期限を守れなかった場合、どうなるでしょうか。
日本年金機構のウェブサイトを見ると、一見すると安心できるものです。
障害状態確認届(診断書)を期日までに提出できていない方は、速やかに提出してください。年金の支払いが一時止まった場合は、障害状態の確認が終了してから、障害の程度に応じて、さかのぼって年金をお支払いします
(出典:日本年金機構ウェブサイト 太字と下線は筆者編集)
この言葉通り、更新手続きの書類提出が遅れたからといって、年金の権利が剥奪されるわけではありません。
2ヶ月に1回支給される年金が一時停止される措置が取られます。
法律用語としては「一時差止」という措置です。
これは、あくまで「書類が提出されるまで、支払いを一時的に保留します」ということ。
ですから、年金が振込が止まっても、慌てないことが肝心です。
とはいえ、「あとからでも遡って全額もらえるなら、少しくらい遅れても大丈夫」と考えるとしたら、極めて危険な誤解です。
この「さかのぼって年金をお支払いします」というシンプルな約束の裏には、専門家でなければ見過ごしてしまう重要なルールが隠されています。
ここだけの話、更新手続きの何が難しいのか
鍵は診断書の「現症日」にある
更新手続きの問題は、単に支払いが遅れることではありません。
その遅れが、取り返しのつかない「金銭的損失」につながる可能性があることです。
その鍵を握るのが、診断書に記載される「現症日(げんしょうび)」です。
聞き慣れない言葉ですが、この「現症日」とは、医師が診察した日付のことです。
この現症日が、誕生月(提出期限となる月)の末日(「提出指定日」といいます)から数えて3ヶ月以内にあるか、それ以降かによって違いが生じます。
特に、提出が遅れた場合にその違いが顕著に現れます。
2つの場合に分けて考えてみましょう。
A:更新の審査の結果、年金が【増額】または【今まで通り】だった場合
このケースは年金受給者にとって、良い結果が出た場合です。
この場合、いつから更新後の金額が適用されるか、以下の2つで変わります。
現症日が【提出指定日から3ヶ月以内】の診断書を提出した場合
誕生月の翌月分から支給されます。
例えば、7月生まれの方が遅れて10月に提出しても、現症日が7月中のものであれば、8月分までさかのぼって支払われます。
一時的に止められていた分もまとめて受け取れるため、金銭的な損失は発生しません。
現症日が【提出指定日から3ヶ月を超えた】診断書を提出した場合
実際に診断書を提出した月の翌月分から支給されます。
例えば、7月生まれの方が11月に診察を受け、11月付の診断書を提出した場合、年金が再開・増額されるのは12月分からです。
この場合、本来もらえたはずの8月~11月分の年金は支給されず、4ヶ月分の金銭的損失となります。
遅れた分だけ、受け取れる年金総額が減ってしまうのです。
診断書の現症日が11月ということは、誕生月である更新期限が過ぎたあと、現症日までの症状がわかりません。
したがって、その間の年金支給はできないという理屈です。
B:更新の審査の結果、年金が【減額】または【支給停止】になった場合
このケースは年金受給者にとって、良くない結果が出た場合です。
つまり、症状が軽くなったと判断された場合です。
この場合は、受給者の生活への影響を考慮したルールになっており、現症日による影響は受けません。
現症日が3ヶ月内であろうとなかろうと、誕生月である提出期限から3ヶ月を経過した月の翌月分から減額・停止となります。
例えば、7月生まれの方が11月に診察を受け、11月付の診断書を提出、その後減額の決定がされたとします。
7月から3ヶ月経過した10月の翌月である11月分から減額となります。
ただ、10月分までは更新前の金額が保障されます。
このように誕生月である提出期限の翌月からいきなり減額となるのではなく、猶予期間を経て減額となるのです。
この違いをまとめると、以下のようになります。
| A 年金増額・今まで通り | B 年金減額・停止 | |
| 現症日が3ヶ月以内 | 誕生月である提出期限の翌月から支給(損をしない) | 誕生月である提出期限から3ヶ月後の翌月から減額・停止 |
| 現症日が3ヶ月超 | 提出月の翌月から支給(提出が遅れた期間分は損をする) |
このように、更新の提出期限を過ぎた場合、年金が増額(または現状維持)する場合に、影響が大きくなります。
せっかく、減額・停止を免れたのに、現症日次第で受け取れるはずだった期間の年金がもらえなくなる。
更新手続きの難しさは実務の運用ルールが知られていないことにあります。
更新手続きを無視すれば最悪の事態に
以上の話は、期限が過ぎても更新手続きを進めた人の話です。
そうではなく、「どうせ症状が軽くなったから、更新しても年金は止まるだろう」と考え、何もしないという選択をする方がいます。
しかし、これは絶対に避けるべきです。
なぜなら、診断書を提出しない場合は、提出した場合よりも早く年金が止められてしまうからです。
診断書を提出、審査の結果、支給停止と判断された場合
誕生月である提出期限の4か月後の支給分から停止します。
つまり、3ヶ月間の猶予があるのは上で説明したとおりです。
診断書を提出しなかった場合
誕生月である提出期限の翌月分から直ちに支給が停止されます。
仮に年金が止まることが分かっていたとしても、診断書を提出するだけで数ヶ月分の年金を多く受け取れる可能性があるのです。
したがって、診断書の提出は必ずするべきです。
なお、診断書を提出しなかったり、審査の結果、支給停止になったりしても、年金を受け取る権利そのものが消滅するわけではありません。
将来、再び症状が悪化した際には、改めて手続きを行うことで、支給の再開を求めることが可能です。
精神障害における更新手続きの難しさ
障害年金の更新手続きは、特に精神障害や発達障害を抱える方々にとって困難が生じます。
精神障害と更新手続きの間に、残酷なほどの矛盾が存在するからです。
つまり、障害年金を受給する理由である症状そのものが、年金を受給し続けるために必要な手続きの遂行を阻むという、矛盾です。
うつ病や発達障害には、集中力や判断力、計画実行能力の低下の症状が伴います。
その症状により、届いた書類の理解、期限管理、医師との連携といった作業が難しくなります。
さらに、「もし更新できなかったら…」という不安が症状を悪化させ、それが悪循環に陥ります。
また、診察室での「パフォーマンスのパラドックス」も深刻な問題です。
日常生活の大半をベッドの上で過ごしていても、診察のために気力を振り絞って身なりを整え、比較的安定して見える姿で医師の前に立つ。
その「良い日のパフォーマンス」が、皮肉にも障害の深刻さを覆い隠し、実態よりも軽い診断書が作成されてしまうリスクを高めるのです。
ここだけの話、みんなのねんきんはこう対応する
まず最も重要なのは、提出期限を守ることです。
2019年7月以降、診断書の用紙は誕生月の3か月前の月末に送付されるようになりました。
準備期間は十分にあります。
通知が届いたら、できるだけ早く行動を開始することが、あらゆるリスクを回避する最善の策です。
次に、医師に自身の状態を正確に伝えるための行動です。
精神障害の審査では、日常生活の困難さをいかに具体的に伝えられるかが鍵となります。
前述した「パフォーマンスのパラドックス」を乗り越え、実態に即した診断書を作成してもらうための準備が重要です。
後編では、更新手続きで損をしないために、みんなのねんきんの対応を含めた専門家の活用について、詳しく解説していきます。
ここだけの話、今回のまとめです

今回の前編では、障害年金更新の裏に潜むリスクと、特に精神障害を抱える方が直面する困難さについて解説しました。
ポイントは以下のとおり。
- 更新手続きの遅延は止まったところまで遡る「一時差止」だが「現症日」のルールにより、損をする場合がある
- 診断書は必ず提出する。 提出しないと提出した場合より早く年金が停止するという不利益がある
- 手続きの困難さはあなたのせいではない。 障害の症状そのものが手続きを阻むという構造的な問題が存在する
障害年金の更新手続きは、自身で行う場合は、手続きの複雑さや精神的な負担は大きいと言えます。
この困難な手続きをより確実に安心して乗り越えるために、専門家へ相談されることを勧めます。
後編で詳しく解説します。

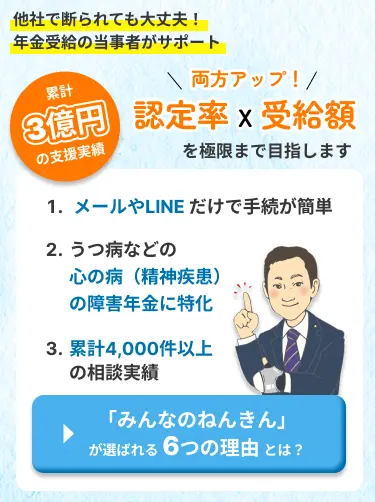
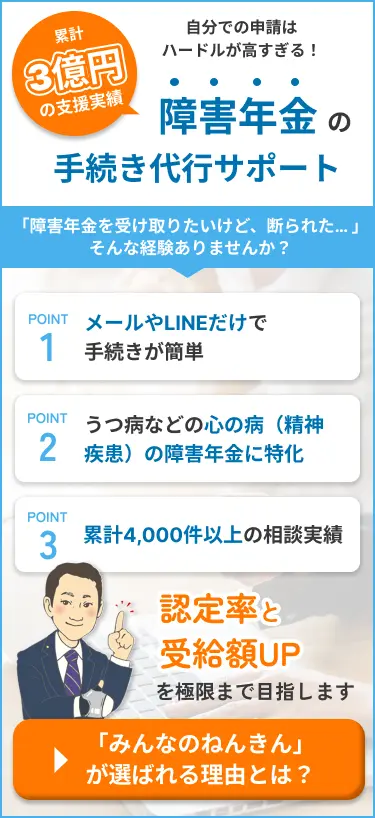

岡田真樹
みんなのねんきん社労士法人代表