
ここだけの話、今回はこんな話です
今回は「年金保険料の納付」という非常に重要なテーマについて、改めて深く掘り下げていきたいと思います。
年金と聞いて「老後のため」と考える方がほとんどではないでしょうか。
もちろん、老後の生活を支える大切な年金ですが、実はそれだけではありません。
もし病気やケガで働けなくなってしまったとき、私たちの生活を支えてくれる「障害年金」という心強い味方があります。
しかし、この障害年金、誰もがもらえるわけではありません。
受給するためには、保険制度としてのルールをクリアする必要があります。
その最も大切なルールが、「保険料納付要件」です。
「もしもの時」に年金がもらえなかった…そんな後悔をしないために、今から知っておきたい大切なポイントを解説します。
ここだけの話、どんな事例?簡単に言うと・・・
自律神経失調症やパニック障害、うつ病で外に出ることも仕事も難しいAさんより、障害年金の相談がありました。
ご自身で「会社を経営していた」とのことだったのですが、詳しく伺うと、法人ではなく個人事業主(自営業)として事業を行っているとのことでした。
ということは、年金の保険料は給料からの天引きではなく、ご自身で保険料を納めるアクションをしないといけません。
国民年金の第1号被保険者という立場となります。
Aさんは、自律神経失調症やパニック障害、うつ病の症状が重く、日常生活や就労に大きな支障をきたしていました。
クリニックにも通い、医師からは就労不能との診断を受けていました。
しかし、ご自身の年金保険料の納付状況を確認してみると・・・。
Aさんはまだ若く「お金が稼げるようになってから後から払えばいいや」と考えていたため、未納の期間が続いていたのです。
ここだけの話、何が問題なの?
この事例から考えなければいけない点は、障害年金は「保険制度である」ということです。
どれだけ障害の程度が重くても、保険料を納めていなければ、障害年金の申請すらできないのです。
Aさんは、「お金が稼げるようになってから後から払えばいいや」という認識でした。
保険制度の理屈でいえば、保険料を払っていないのに、保険金を受け取ることはできないでしょう。
もしAさんが会社員(厚生年金)だった場合は、保険料は給与から天引きされるため未納になることはありません。
しかし、個人事業主である第1号被保険者はご自身で保険料を納付しなければなりません。
体調を崩して金銭的にも苦しくなった時に、ついつい後回しにしてしまいがちですが、それが将来の大きなリスクにつながるのです。
そんな保険料を納めていないAさんですが、救済される可能性はあるのか。
公的年金は民間の保険ではなく社会保険です。なにか解決の道があるかもしれません。
今回はそこが問題となります。
保険料を納めていることは障害年金3要件の1つ
そもそも、障害年金を受け取るためには3つの要件を満たす必要があります。
障害年金受け取りのための3要件
- 初診日要件:障害の原因となった傷病について初めて医者に掛かった日(初診日)に国民年金または厚生年金保険に加入していること
- 保険料納付要件:初診日の前日時点で、年金保険料の未納が少ないこと
- 障害認定日要件:障害認定日(初診日から1年6カ月経った日)に法律で定められた障害状態であること
この中で今回取り上げるのは2つ目の「保険料納付要件」です。
この要件は、病気やケガで初めて医師の診察を受けた日、つまり「初診日」がポイントです。
この初診日の前日までに、年金保険料をしっかり納めているかどうかが問われます。
保険料納付要件には、2つのパターンがあります。
実は公的年金における障害年金は1ヶ月でも未納になったらNGというものではなく、ある程度の未納は許容されています。
ここは民間の保険とは違う点と言えるでしょう。
以下の2つのパターンのうち、どちらか1つの要件を満たせばOKなんです。
具体的に見ていきましょう。
原則ルール 未納が3分の1未満である
まずは原則のルール。
これまでの年金加入歴のうち、3分の2以上保険料を納付または免除されていることが必要です。
逆に言えば、未納の期間が3分の1未満であれば良いということ。
多少は未納の期間があっても許されるんですね。
もう少し具体的に言えば、
初診日の前日において、初診日のある月の前々月までの期間で、保険料を納めた期間と免除された期間を合わせると、全体の3分の2以上あることが必要です。
具体的に事例で考えてみましょう。
原則ルールを事例で考える
- X月Y日に医者に診てもらった(初診日)
- X月Yー1日の時点で、X月の前々月までの国民年金に強制加入(20歳)してからの期間は10年(120ヶ月)だった
この場合、保険料納付要件をクリアするためには、120か月のうち
保険料を実際に納めた期間
保険料を免除・猶予された期間
を合わせた期間が、80か月以上(120×2/3=80)必要となります。
もし未納期間が41か月以上あると、この要件はクリアできません。
また、年金保険料はあとからまとめて納めることができますが、X月Y日以降に過去の分を納めてもNGです。
X月Y−1日の時点で判定するからです。
特例ルール 直近1年は未納がない
次にもう1つのルールを見てみましょう。
もし原則ルールで要件を満たせなくてもまだ可能性はあります。
過去にどんなに未納の期間があったとしても、直近の1年間に未納がなければ救済される特例があるからです。
特例ルールを事例で考える
- X月Y日に医者に診てもらった(初診日)
- X月Yー1日の時点で、X月の前々月までの国民年金に強制加入(20歳)してからの期間は10年(120ヶ月)だった
- 20歳からの9年間は未納だった
- X月の前々月までの直近1年間は全て保険料の免除を受けていた
この場合、全体の9割は未納ですが、直近1年で未納がない(保険料の免除を受けていた)ので要件をクリアします。
民間の保険であれば考えられない事態。
また、「免除」はきちんと手続きをしたうえで認められるものなので、「未納」とは異なります。
仮に納められない状態であったとしても、ほったらかしにしていたらダメなのです。
この特例ですが、原則ルールにはない注意点がいくつかあります。
- 令和18年3月31日までに初診日がある人に対する期間限定措置
- 65歳以上の人にはこの特例は使えない
- 連続した直近1年(12ヶ月)の中で未納が1ヶ月でもあればNG
もちろん、X月Yー1日の時点で判定されるのは原則ルールと同様です。
ここで、Aさんの話しに戻ります。
Aさんは、体調を崩してすぐに初診日を迎えています。
その前日の時点で納付要件を満たしていなければいけません。
「後から払えばいいや」と考えていたAさんは原則のルールは満たせていませんでした。
また、体調を崩してすぐに初診日を迎えたため、特例にも該当しません。
Aさんの状態であれば、年間約80万円の障害年金の可能性がありました。
結果、Aさんは、病気の状態がどれだけ重くても、障害年金の受給は叶わなかったのです。
ここだけの話、もしもの障害年金に備えて今すぐできること!

と諦めていませんか?
繰り返します。
障害年金は、初診日の前日までに納付や免除申請ができていなければ、納付要件を満たせません。
つまり、体調を崩してから後で慌てて納付しても手遅れになってしまうのです。
しかし、まだ間に合う人もいます。
そうならないための、今からできることをお伝えします。
自分で保険料を納める義務があるかを確認すべし
20歳から60歳未満の日本在住の方は、国民年金に加入し、保険料を納める義務があります。
この方は上でも説明しましたが国民年金の「第1号被保険者」という区分の人です。
特に誤解しやすいケースがありますので確認しましょう。
厚生年金加入の配偶者に扶養されている場合
専業主婦(主夫)など、会社員や公務員で厚生年金に加入する配偶者に扶養されている方は国民年金の「第3号被保険者」という区分となります。
この場合は、ご自身で保険料を納める必要はありません。
配偶者の加入する厚生年金制度が第3号被保険者分の保険料を負担する仕組みだからです。
親に扶養されている学生や無職の場合
たとえ親の扶養に入っていても、第1号被保険者であれば、保険料を納める義務があります。
同じ扶養でも、配偶者に扶養されている専業主婦(主夫)とは大きく違いますので注意です。
社会保険に加入していないアルバイト・パートの場合
アルバイトやパートでも労働時間や給料によって社会保険(厚生年金・健康保険)に加入できる場合があります。
そうでない場合、上で説明した第3号被保険者でなければ、第1号被保険者になります。
第1号被保険者であれば、ご自身で保険料を納める義務があります。
学生の場合
学生であっても20歳になれば、第1号被保険者に該当します。
ただし、学生専用の猶予制度があり、「学生納付特例制度」を利用できます。
この特例は自分で申請しなければいけません。
手続きをしていなければ、依然として納める義務があり、納めなければ未納となってしまいます。
未納にしないために具体的な行動に移すべし
ご自身が国民年金の第1号被保険者であるなら、今すぐ具体的な行動に移しましょう。
「ねんきんネット」で納付状況を確認する
まずは、ご自身の年金記録がどうなっているかを知ることが最初の一歩です。
「ねんきんネット」に登録すれば、スマートフォンやパソコンから24時間いつでも納付状況を確認できます。
もし未納期間があれば、どの月に納付が必要かひと目でわかります。
電子納付(スマホ決済・クレジットカード)を活用する
かつては、保険料を納める手段は納付書を持って金融機関かコンビニで納めるしかありませんでした。
ここ数年で環境がかなり変わりました。
現在は、納付書がなくてもスマートフォン決済やクレジットカードで支払うことができます。
保険料の免除・猶予制度を申請する
もし納めることが難しい場合は、未納のままにしてはいけません。
ほったらかしにするのが一番危険なのです。
こんなときは、免除・猶予制度を積極的に利用しましょう。
これらの制度を申請して認められれば、保険料を払わなくても、上で説明した納付要件の対象期間になります。
この申請も、「ねんきんネット」を通じてオンラインで手続きが可能です。
ここだけの話、今回のまとめです

今回は、保険料を納めることの重要性について解説しました。
ポイントは以下のとおり。
- 障害年金を受け取るためには「保険料納付要件」を満たす必要がある
- 保険料納付要件は2つのルールがあり、どちらかを満たせば良い
- 保険料納付要件の原則のルールは未納が3分の1以下であること、例外のルールは直近1年で未納が無いこと
- 全ての年金加入者が自身で保険料を納めるわけではない。国民年金の第1号被保険者のみである
- 保険料を納められないなら免除制度を活用すべき。ほったらかしが一番危険である
今回のAさんの事例を通して、障害年金が単なる福祉制度ではなく、保険制度としての側面を持っていることをご理解いただけたかと思います。
Aさんは将来に渡り受けられるはずだった年間80万円が消えてなくなりました。
2年で160万円、3年で240万円・・。
考えてみると恐ろしいことです。
私がこの制度について何度もコラム化しているのは、この制度によって生活が救われる人が一人でも増えてほしいと心から願うからです。
年金制度は複雑に感じられるかもしれませんが、まずは「知ること」が未来を守る第一歩です。
ご自身の年金記録がどうなっているか、「ねんきんネット」などで確認してみてください。
Aさんのような方がいなくなるまで、私たちは何度でも保険料を納めることの大切さを訴え続けなければならないと思っています。
それが障害年金を手掛ける私たちの責務だからです。

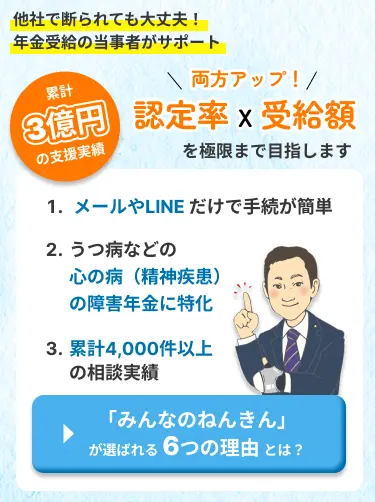
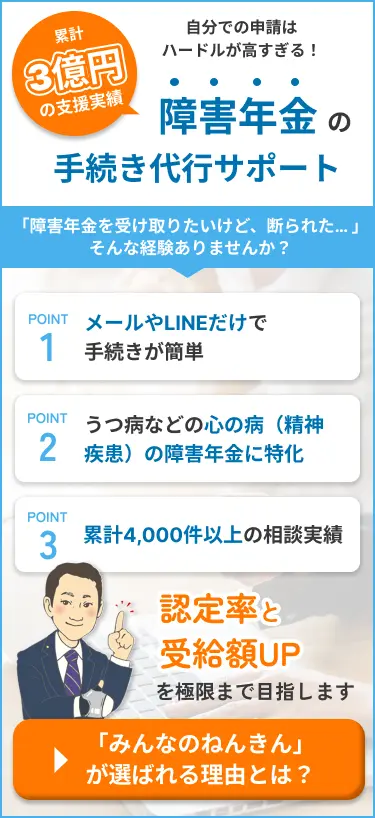

岡田真樹
みんなのねんきん社労士法人代表