
ここだけの話、今回はこんな話です
障害年金の請求に必要な診断書。
今回は障害年金を受け取るために知っておくべき診断書依頼のための重要なポイントと、みんなのねんきんではどのようにサポートしているのかを解説していきます。
障害年金の申請を検討されている方はもちろん、すでに手続きを進めているけれど不安を感じている方も、参考にしてください。
ここだけの話、障害年金の請求に診断書は超重要なのです!
障害年金における診断書の役割とは
「うつ病」「双極性障害」「統合失調症」「発達障害」「知的障害」
みんなのねんきんには様々な障害のご相談が寄せられますが、精神障害がもっとも多い状況です。
どのような障害であっても、障害年金を受け取るためには以下の3つの要件を満たさないといけません。
障害年金受け取りのための3要件
- 初診日要件:障害の原因となった傷病について初めて医者に掛かった日(初診日)に国民年金または厚生年金保険に加入していること
- 保険料納付要件:初診日の前日時点で、年金保険料の未納が少ないこと
- 障害認定日要件:障害認定日(初診日から1年6カ月経った日)に法律で定められた障害状態であること
この中の3つ目、「障害認定日要件」は「法律で定められた障害状態であること」となっています。
年金を決定するかどうか審査する側が障害状態をどうやって確認するかというと、それは医師が作成した診断書しかありません。
したがって、障害年金の請求手続きにおいて、医師の「診断書」を提出し、それが障害状態に該当するなら、3つ目の要件を満たすことになるわけです。
とはいえ、
精神を患っている方にとって、診断書の作成依頼は容易ではありません。
というのも、
精神の障害ゆえに外部から判断がつかない・理解がされないことが多いからです。
このような場合、どのような問題が生じるのでしょうか。
医師に対してその症状を伝えられるのか
精神障害で障害年金を請求する、多くの方が抱える強い不安。
それは、
「医師に自身の日常生活の困難さが、きちんと伝わっているのだろうか?」
というもの。
精神障害の特性として、気分の波が激しい、症状が変動しやすいといった点があります。
- 受診時にたまたま調子が良かったために、本来の辛さや生活への支障が医師に十分に伝わらない
- 倦怠感や意欲の低下が強く、自分の状況をうまく言葉で説明できない
そのため、
「この患者は、なんとか日常生活を送れていそう…」
「この方は、簡単な家事ならできていそう…」
と、実際とは異なる印象を医師に与えてしまうことがあります。
例えば、うつ病の方であれば、医師に伝える意欲が湧かなかったり、医師に質問されても返答することが億劫になったりするため、受診時に「問題ありません」と答えてしまうことがあるかもしれません。
双極性障害の方であれば、躁状態と鬱状態を繰り返す中で、受診のタイミングによって医師に伝えるべき情報が異なってしまうことがあります。
統合失調症の方であれば、幻覚や妄想といった特有の症状があるものの、それを医師に打ち明けることに抵抗があったり、どのように説明すれば良いか分からなかったりすることもあるでしょう。
さらに、精神障害では、、睡眠障害やパニック障害、不安障害といった他の症状を併発している場合もあります。
これらの複合的な要因が日常生活に与える影響を、限られた診察時間の中で医師に正確に伝えることは、決して容易ではありません。
うまく伝わらないとどうなる?
それでは、これらの症状を医師にうまく伝えられないとどうなるでしょうか。
障害年金手続きにおける診断書の役割を考えれば、大きな問題が生じます。
それは、3要件の3つ目の「障害状態」の審査において、医師が作成する診断書が、年金の決定・等級を左右するからです。
日本年金機構などの審査機関は、大部分を提出された診断書で「障害状態」の判断をしています。
診断書記載の傷病名、発症からの経過、治療内容、そして現在の精神症状や、それらが日常生活や仕事にどのような影響があるか・・・。
特に精神障害の場合、身体障害のように目に見える症状や数値化されたデータがほとんどありません。
医師の診断書における様々な記述が、審査の行方を大きく左右するのです。
もし、診断書の内容が、ご自身が日々感じている日常生活における具体的な困難さと大きくかけ離れていたり、それらが十分に伝わらない曖昧な表現になっていたりするとどうなるでしょうか。
本来であれば受け取れるはずの等級よりも低い等級で認定されてしまったり、最悪の場合には不支給の可能性さえあるのです。
医師の医学的な意見に基づいて作成される診断書は、信ぴょう性の高い審査資料とされています。
このように診断書は、障害による生活の困難さを医師の視点から証明する重要な書類であることを認識する必要があります。
ここだけの話、みんなのねんきんはこんなサポートをする!
年金決定・等級を左右する大事な診断書。
どうすれば的確に現状を反映した診断書を作成してもらえるでしょうか。
障害年金を請求される方が、ご自身の状況を正確に診断書に反映してもらえるよう、みんなのねんきんでは以下のような独自のサポートを行っています。
最初に、医師に診断書を依頼する前に、年金記録、就労歴、病気の経歴などの情報を収集します。
その情報を整理し、発症の契機、病気のタイプによるこれまでの影響などを把握します。
その後、本人及び必要に応じてご家族から、丁寧なヒアリングを実施します。
精神的な症状だけでなく、日常生活における具体的な困りごと、例えば、
- 食事の準備や片付けができない
- 入浴や着替えが億劫でなかなかできない
- 買い物や金銭管理が困難である
- 他人とのコミュニケーションがうまくいかない
- 外出することができない
など、細部にわたるまで詳しくお話を伺います。
この丁寧なヒアリングを通じて、私たちは一人一人状況を深く理解し、その情報を基に、医師への診断書作成を依頼する際に役立つ、個別の資料を作成します。
この資料には、ヒアリングで把握した日常生活の状況や、就労状況、病状の経過などを、分かりやすくまとめます。
特に、精神障害の診断書で重要となる、日常生活能力の判定項目について、具体的なエピソードを交えながら、医師が評価しやすいように整理します。
この判定項目は以下に分類されます。
- 適切な食事
- 身辺の清潔保持
- 金銭管理と買い物
- 通院と服薬
- 他人との意思伝達及び対人関係
- 身辺の安全保持及び危機対応
- 社会性
これらの項目について、本人が「できる」のか「できない」のかを医師が評価するわけです。
資料作成時には、医師が多忙な診察業務の中で、効率的に状況を把握できるよう、専門的な知識に基づいた工夫を凝らしています。
例えば、診断書の記載要項や、精神障害の等級判定ガイドラインなどを踏まえ、医師がどのような情報を必要としているかを考慮しながら作成します。
また、必要に応じて、過去の診断書や受診状況等証明書などの参考資料も添付します。
つまり、一言で言えば、
一人一人に合わせた丁寧なヒアリングにより、医師が状況を把握しやすいサポート資料の提供
がみんなのねんきんのサポート内容となります。
このような資料があることで、医師も限られた時間の中で、本人の日常生活における困難さをより深く理解し、適切な診断書を作成することが期待できます。
実際、ある相談者から「手続代行はみんなのねんきんに依頼するよう医師に言われた」と、弊社をご紹介いただくことがあります。
これまでの弊社のサポートについて評価していただいた結果と感じています。
ここだけの話、今回のまとめです

今回は、障害年金を請求する際の診断書の重要性について解説しました。
ポイントは以下のとおり。
- 診断書は障害年金の3要件のうちの「障害状態」を決めるための重要な資料である
- 精神疾患においては、日常生活の困難さを医師に的確に伝えられないことがある
- 診断書の内容が事実と異なると、実際よりも低い等級や最悪の場合、不支給となる可能性もある
- 事実に即した診断書を作成してもらうためにみんなのねんきんでは適切なサポート資料を医師に提供している
うつ病などの精神障害で障害年金を申請する際、医師の診断書は、ご自身の状況を証明する非常に重要な書類です。
しかし、精神障害の特性上、その苦しさが医師に伝わりにくく、診断書の内容が不十分になってしまうケースも少なくありません。
みんなのねんきんでは、丁寧なヒアリングと、医師に分かりやすい資料作成を通じて、精神障害をお持ちの方が障害年金を受給できるよう、しっかりサポートしています。
もし、診断書の作成や申請手続きについて不安なことがあれば、一人で悩まずに、ぜひご相談ください。
皆さまが安心して障害年金を受け取れるよう、親身になってサポートいたします。

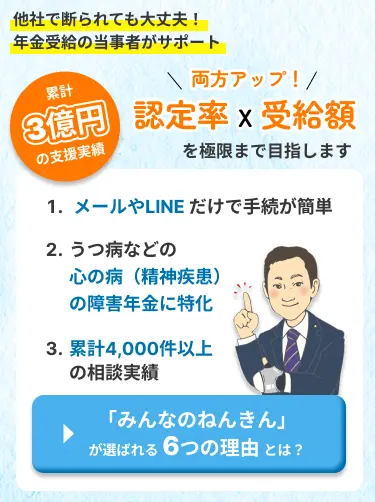
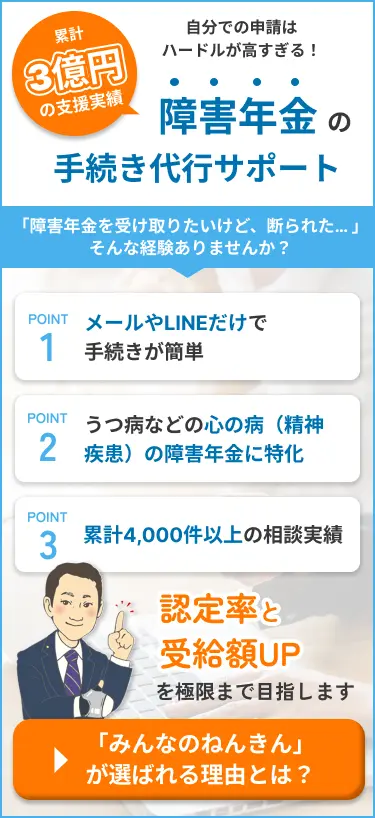

岡田真樹
みんなのねんきん社労士法人代表